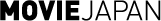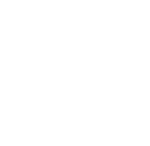- 和歌山 和歌の浦
- 和歌浦湾はシラスなどが取れる資源豊かな港であると共に国指定の名勝です。和歌浦市南岸の景勝地の総称として和歌浦湾と呼ばれます。太古の昔、聖武天皇も魅せられたと言われる、玉津島山と呼ばれる岩山や不老橋の元を流れる和歌川の河口から望む干潟。そしてそこから見る美しい日の出日の入など、和歌浦十景と呼ばれる景色に人々は心奪われます。
- 山梨 本栖湖 富士芝桜まつり
- 富士五湖のひとつ本栖湖近くの樹海の中に、80万株からなる広大な芝桜の花園が広がります。芝桜が咲く4月中旬〜5月は、まだまだ富士山の5合目以上に残雪が残り、富士山を眺めるには最高のシーズン。しかも富士山麓は新緑真っ盛りです。赤とピンクの絨毯の向こうに、青い空とまだ雪が残る富士山。なだらかな芝桜の花畑は得も言えぬ美しさです。
- 高知 仁淀川 紙のこいのぼり
- 高知県にある仁淀川では、毎年5月、特産品である不織布を使って作られた紙こいのぼりが清流を泳ぎます。仁淀川橋の上から眺めることの出来る鮮やかなこいのぼりは、約300匹。空ではなく水中を泳ぐこいのぼりが、爽やかな初夏の訪れを感じさせます。その他にも、川舟の体験や吾北清流太鼓の演奏などを楽しむこともできます。
- 長野 菜の花と鯉のぼり
- 残雪の北アルプスを見渡す菜の花畑。まるで黄色い絨毯を目一杯に広げたような風景が春の訪れを教えてくれます。5月初旬には菜の花畑の上空をたくさんの鯉のぼりが悠々と泳ぎます。山の雪解け水によって出来る池には、凛とした姿の北アルプスと青い空が映り込み、爽やかな絵葉書のような光景を楽しむことができます。
- 長野 花桃の里 花桃まつり
- 花桃の里は日本一の桃源郷と呼ばれ、春には約5000本の花々が密集して咲き誇ります。赤白ピンクの花桃は、まるでパッチワークのような味わいを見せてくれます。
花桃は桜や梅よりも花が大きく、見栄えが良いのが特徴です。4月~5月に開催される花桃まつりでは、柔らかな色合いの花々と鮮やかな鯉のぼり、その両方が楽しめます。
- 奈良 喜光寺
- 喜光寺は法相宗の別格本山で、菅原氏のゆかりの地であることから「菅原寺」とも呼ばれています。奈良時代の僧行基が没した地として知られています。本堂は重要文化財に指定されています。行基が東大寺大仏殿を建立する際の雛形として建てたという言伝えから「試みの大仏殿」とも呼ばれます。また、蓮の名所としても有名です。
- 北海道 大雪山国立公園
- 大雪山国立公園は日本で最も広い国立公園です。北海道の屋根とも呼ばれ、旭岳を主峰とする大雪山連峰や十勝岳など多くの山が連なっています。アイヌの人々はこの地を「カムイミンタラ」神々の遊ぶ庭と呼んでいました。季節ごとに鮮やかな高山植物が咲き、希少な動物たちも生息しています。近辺には温泉も多く湧き出ています。
- 静岡 柿田川湧水群
- 柿田川は静岡県を流れる一級河川です。日本一短い一級河川と言われていますが、大量の湧水を水源とする日本でも珍しい川で、日本三大清流に数えられています。その他にも、名水百選や天然記念物、日本の秘境100選にも選定されています。透明度の高い川なので、ふつふつと湧き出る水の様子を肉眼で観察することができます。
- 東京 旧古河庭園 春のバラフェスティバル
- 旧古河庭園は、国指定の名勝です。武蔵野台地の地形を活かして造られた異国情緒あふれる敷地内は、小高い丘に洋館が建ち、斜面には洋風庭園が、低地部分には日本庭園が配されています。
元々は陸奥宗光公の邸宅だった場所が英国人のコンドル博士の設計で、美しくバラが咲き誇るまるで絵画のような庭園に生まれ変わりました。
- 東京 浅草 三社祭
- 三社祭は浅草神社で毎年5月に3日間を通して行われる勇壮な祭り行事です。東京の初夏を代表する風物詩のひとつとして広く知られています。
囃子屋台をはじめ、華やかな舞いを踊る大行列が浅草の町を練り歩きます。また、伝統的な式典が行われたり、戦前に徳川家光公より寄進された歴史ある神輿の担ぎ出しがされたりします。
- 京都 瑠璃光院 春 青もみじ
- 山門をくぐると木漏れ日の美しさに光る苔の緑が迎えてくれます。数寄屋造りの本堂の二階にあがると、大きく開けたガラス戸の向こうに一面の紅葉。春は新緑の青い世界が室内の家具にも映り込み、さらに鮮やかな世界が広がります。飛鳥時代に天武天皇が、八瀬の風呂釜で傷を癒したとされる頃から、人々の保養地であったと言います。
- 新潟 佐渡 竜王洞
- 竜王洞は海底溶岩の浸食によってできた溶岩洞窟です。天気の良い日には、日差しを受け淡く光ることから佐渡版の青の洞窟と呼ばれています。
シーカヤックやモーターボート、または徒歩で、ひんやりとした空気に満ちた洞窟内に入ることができます。洞窟内を散策すると、地球の内側を見ているような気分を味わうことができます。