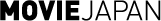しごと
- 奈良漬
- 奈良漬は1300年以上前から食されていた歴史ある漬物です。酒の名産地である奈良県がその発祥で、白瓜や胡瓜、西瓜や生姜などの野菜を塩漬けにした後、酒粕に漬けてつくられます。長期保存が可能であり、季節を問わずに様々な野菜を食べることができます。旨味や香りに優れていて、美しいべっこう色をしているのが特徴です。
撮影協力・森奈良漬店
- 新潟 佐渡 無名異焼
- 無名異焼は、佐渡の代表的な伝統工芸品です。高温で焼き締められた非常に固い陶器であり、佐渡金山から産出する酸化鉄を多く含んだ茜色の土から造られています。
叩くと金属のような澄んだ音が鳴るのが特徴です。また、焼く際に炎の当たった部分が黒く変色することから、土の赤と黒色部分の対比が美しい工芸品でもあります。(撮影協力 玉堂窯元)
- 徳島 半田そうめん
- 地の利を生かし作られる、強い歯ごたえと喉越しの良さ。その美味しさは半田そうめん音頭にも歌われます。特徴的なのは太さで、分類上はひやむぎですが、半田手延べそうめんは、江戸からの文化も含みそうめんと表記します。標高差が300mある半田の町。熟成時間や水、塩加減等は製造所によって変わり、その違いも楽しめます。
- 徳島 門松作り
- 門松はお正月に年神様を迎える目印であり、またその依り代として家の前に置かれます。平安時代頃よりあったとされ、初めは松のみを飾るものでした。松は葉が落ちないので縁起が良く、神の宿る木と言われます。また繁栄を意味する竹を斜めに切ったのは徳川家康と言われ、負けた戦の悔しさを忘れないためでした。
- 鹿児島 さつま揚げ
- さつま揚げは名前のとおり薩摩の国でできた食べ物です。琉球との交流が深くあった、島津斉彬公の時代、 琉球から揚げ物のチキアーギが伝わり、日本にあったかまぼこ作りに加わって「つけあげ」になりました。これが関東に伝わる際にさつま揚げになったと言われます。 現在では栄養豊富なヘルシー料理として再び注目を集めています。
- 鹿児島 天然塩作り
- 塩の歴史は古く、縄文時代終わり頃の製塩土器が鹿児島から見つかっています。また江戸時代後期には島津斉昭によって製塩が奨励されました。塩田は県の南側に多く、南洋から来た黒潮のきれいな海水が利用されます。ミネラル分を豊富に含み、旨味のどの部分を残すかによって味が変わるため職人や土地ごとに特徴があり、色々な天然塩が楽しめます。
- 鹿児島 枕崎 鰹節作り
- 日本料理に欠かすことのできない伝統食・鰹節。枕崎は、日本有数のカツオの水揚げ量を誇り、また、江戸時代中期から鰹節を製造してきた、鰹節生産量日本一の町です。
鰹節は、養老律令(718年)の時代に原形が見られる日本古来の調味料で、以来、長きにわたって日本の味を支え続けてきました。
- 香川 うどんづくり
- 香川県のと言えば「讃岐うどん」。「足踏み」は讃岐うどん独自の製法で、強いコシを生む大切な作業。鍛えられた生地を麺棒に巻き付け、叩きつけながら延ばされたうどんは巨釜でゆで上げられ、いりこで取った澄んだ出汁でいただきます。
- 金沢 金箔工芸
- 10円硬貨ほどの大きさの地金を、畳4枚分にまで延ばす職人技から生み出される金沢箔は全国シェアの98%を占めているほどです。繊細な作業を経た金沢箔は仏壇や金屏風、西陣織、漆器など多くの工芸品や美術品などに用いられています。
- 神戸ビーフ
- 神戸港が開港された際、但馬牛を食べたイギリス人がその味を絶賛したことが始まりといわれ、外国へ輸出されたり、全国に流通するようになりました。欧米を中心に知名度が高く、「Kobe Beef」として人気を集めています。
- 広島焼き
- 薄く伸ばして焼いた生地の上に野菜や肉といった具を重ねてひっくり返し、生地でふたをして「蒸し焼き」にするのが特徴で、具と生地を混ぜて作る大阪のお好み焼きとは全く異なり、中華麺ともやしを使用するのが広島オリジナル。
広島ではもちろんこれが「お好み焼き」です。
- 会津若松市プロモーション映像 史季彩再 「街中文化散策」
- 江戸時代からの多くの伝統文化が息づく会津。職人の技が施された美しい工芸品や、古くから伝わる日本酒や郷土料理の数々を紹介します。